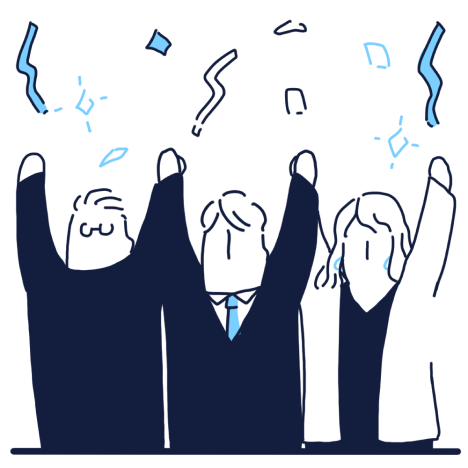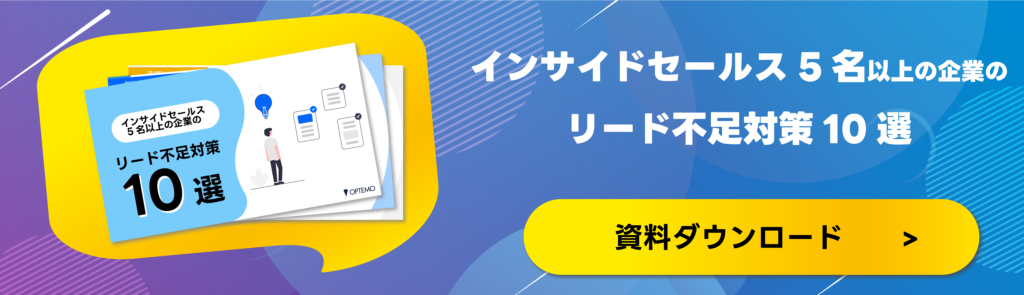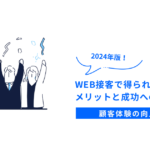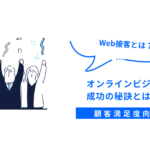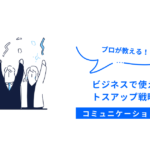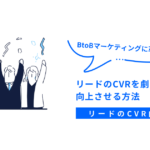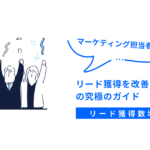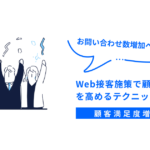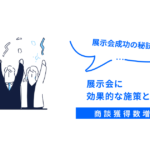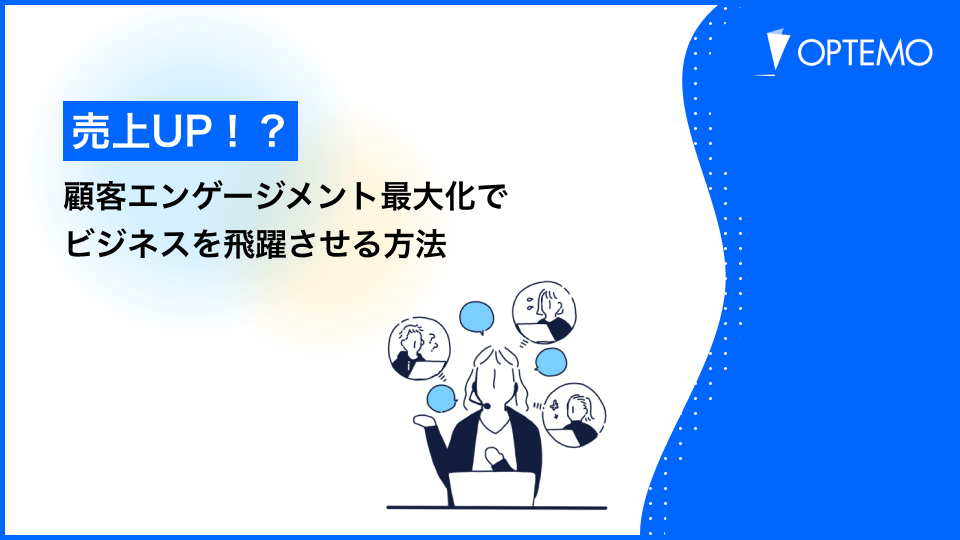BtoBでリード獲得したい時にアウトバウンド以外の方法を知りたい
目次
WEB接客ツールをBtoBで検討するタイミング
この記事はWEB接客ツールをBtoB(B2B)で使ってみたいという方のために、方法や施策を例を用いて紹介しています。SaaS企業に限らず、全ての企業にとって新規リードの獲得は重要な要素となります。アウトバウンドコールを使って顧客リストに対してインサイドセールスがアプローチしている会社もありますが、
・リストが足りなくなった、変わり映えしない
・新規リードをもっと増やしたい
・アウトバウンドのアポイント率がどうにも上がらない
・リード獲得の方法はいろいろやった
・MAを使ったメルマガやスコアリングが停滞している
・WEBからのCV(コンバージョン)をもっと増やしたい
といった声をよく聞きます。

そこで施策としてWEB接客ツールを使った方法によるリード獲得が挙げられます。BtoCでの活用は普段の生活の中でも事例として体感していますが、BtoBでリード獲得するためにWEB接客ツールをどのように使うと成功できるのかは中々調べることができません。
WEB接客ツール以外で良く行われる施策
(オンライン)展示会
従来は東京ビッグサイトや幕張メッセで開催される大規模な展示会でのリード獲得が可能でしたが、リアルイベントの縮小、中止に伴い、オンライン展示会を含むイベントも数多く開催されています。
オンライン展示会の場合、リアル展示会で可能であった「その場で商談化する」が難しく、リード情報を獲得するまでがスコープとなるケースがメインです。その後のナーチャリングが準備されていないと、単なるリストになってしまい、先方へ連絡が取れなくなるということもよくあります。
MA(Marketing Automation)ツールを使ったメルマガによってナーチャリングを整備している企業も多いですが、イベント経由のナーチャリングの場合、MAを送る頻度や送るコンテンツの質によって長期化することがあります。
近年はオフラインでの展示会も来場者数が回復傾向にあり、展示会を活用して新規リードを獲得する企業もBtoBで増えてきています。展示会は、出店費用だけでなく什器や装飾など費用が大きくかかることが特長ですが、ブースへの来場者とその場で深い話を行い、その場でアポイントやネクストを握って獲得することもできるため、効果を短期で出しやすい施策となります。オフラインの展示会の場合、出展位置や出展する展示会を十分に精査する必要があります。様々な主催会社が展示会を開催しているため、自社のターゲットとなるお客様が来場する展示会を選ぶ必要があります。

(副業)マッチングサービス
ビジネスマッチングツールも多様な種類が拡大し、リファラルを使ったリード獲得の方法も手法として考えられます。しかし、そのマッチングサービスに登録している方の属性や温度感は偏っていることもあり、特定のセグメントを獲得する方法に留まることが多いです。
特に、従業員5名以下の企業の経営者が数多く登録しているプラットフォームが多い傾向です。
リモートワークの増大と多様な働き方の拡大によって、副業(複業)を解禁した企業が増えた結果、副業も含んだマッチングサービスも増えています。
後述のアポイント代行と副業を組み合わせたサービスもあり、ビジネスサイドの人材であっても、BtoBであってもマッチングサービスを使ったアポイント獲得、リード獲得もあります。
WEB広告
リスティング広告、ディスプレイ広告といった広告が可能であり、Google広告(Google Adwords)やFacebook広告(Instagram広告)、Twitter広告など、どのプラットフォームへ出稿するかによって獲得できる属性も異なります。
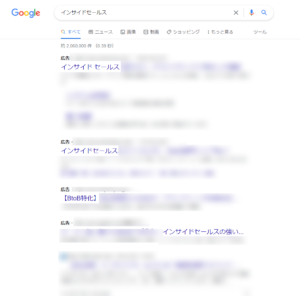
Google広告やFacebook広告、Twitter広告の場合は広告代理店も多く、リスティング広告やディスプレイ広告のノウハウや知見もWEB上に数多くあるため、ファネルとして費用対効果を計算しやすくなります。
但し、どのキーワード、属性、クリエイティブによって「当たり」となるかはトライ&エラーが必要であり、機械学習で「最適な広告パフォーマンス」には3か月程度期間が必要になります。
業界や商材によってGoogleだけでなくYahoo!広告が適しているケースもあり、どの媒体にどんな広告を出すかによってパフォーマンスが異なります。
近年、サードパーティーcookieの規制が厳しくなっている傾向であり、ファーストパーティーcookieの重要度が上がっています。しかし、依然としてメインのリード獲得導線として設定している企業が多く、広告の方程式を確立しやすい方法と考えられます。
WEB広告についてはマーケティング部門が主導して行われることが多いですが、マーケティング部門とインサイドセールスが一緒に企画していくことで、WEB広告経由の新規リードへシームレスにアプローチすることができます。
SEO強化
自社でオウンドメディアを運営し、コラムやブログ、事例やお役立ち情報を定期的に投稿し、SEO(Search Engine Optimization)を強化する方法になります。SEOによる集客を実現すると、Google検索やYahoo!検索、Bing検索など検索エンジン経由で自社のWEBサイトへ流入する母数が増加し、CVR(ConVersion Rate)に従ってリードを多く獲得することができます。
しかし、強化するキーワードによっては競合度が高く、Google検索などで上位表示するためには
・記事の数、文字数
・キーワードの数
・コンテンツの質
・直帰率やクリック率
といった様々な要素によってWEBサイトの品質を上げる必要があります。
競合度の高いキーワードで上位表示させることは難易度が高いこともあり、継続的に質の高い記事を公開し続けることは覚悟が必要です。
さらに、SEOでGoogle検索で上位表示されるまでには時間がかかることもあり、記事を公開してすぐに流入が一気に増えることは難しく、長期的・継続的に品質を上げ続けることが必要です。
例えば、競合度の高い「インサイドセールス」というキーワードの場合、上位のWEBサイトは13,000字以上のコンテンツ、見出しが70個となっているページも複数あり、さらに単発の記事ではなく同様の品質の記事が多数投稿されていて上位表示を実現しています。
メディア出稿
BtoBでも業界ごとにメディアがあり、メディアに広告を出稿することでリード獲得が可能です。メディアサイトでは数十~数百セッションの流入、PV(Page View)があるため、その集客力を活用したリード獲得が可能です。
主に「メディア内でのバナー広告」、「タイアップ(特集)ページ」、「メルマガでの広告」の3種類が多く、各メディアのメディア資料をダウンロードするとどのくらいのPVが見込めるかが計算できます。また、メディアの営業担当者へ相談すれば、どの程度のCVが見込めるかなども共有してもらうことができます。
特定セグメントへ一気にアプローチできる一方、特定セグメントを集客しているメディアがあるかどうか、メディアからのCVの温度感のコントロールが必要となります。
リード獲得の手法として「メルマガ→イベント」の後に検討されることが多いと経験則から感じています。
投資家からの紹介
スタートアップによってはVC(Venture Capital)やエンジェル投資家といった投資家が株主として参画されていることも多いです。投資家からの紹介は非常に強く、お互い出資先であることもあるため、お互いに信頼した状態でリード獲得(そのまま商談)ができます。
メリットとしては商談までのスピードが速く、かつ決裁者やキーマンのリード獲得ができる事です。一方で、投資家が紹介できるリード数には限界があり、永遠に投資家からの紹介に依存することはできません。
「どうしてもここのリードを獲得したい、商談したい」という際に非常に心強い手法かと思われます。
ウェビナー
リアルでのセミナーではなく、近年はウェビナーが数多く開催されています。Zoomを使うとすぐに開催できるため、各社でのウェビナーやいくつかの企業が合同でウェビナーを共催することも多いです。
無料で参加できるウェビナーが多く、気軽に参加できる一方、参加者のドタキャン対策や集客の方法が必要であり、参加者に対して終わった後のフォローアップをする必要があります。(無料ウェビナーの場合、申込み対比で70%程度の出席率が相場化と考えています。)
しかし、参加者に対して「一定時間自社の魅力などを伝えることができる」という点で、商談化に持って行きやすい方法となり、BtoB企業のリード獲得手法として活用されています。
ウェビナー参加時にフォーム入力を用意するケースがほとんどであるため、参加登録の時点でリード獲得が可能です。
イベント出展
展示会ではないイベントに出展することもリード獲得が可能です。イベントの種類は様々な種類がありますが、オンライン・オフライン問わず「どんな参加者がどのようなマインドで参加しているか」がキーポイントになります。
イベントによってはセミナーのようなセッションをオプションでつけていることもあり、セッションで参加者へ自社の魅力を紹介し、ミニブースで資料ダウンロードを促すという流れもあります。イベントの場合、獲得したリードが「情報収集レベル」であることも多いため、MarketoやHubspot、PardotのようなMAツールを使った後追いの仕組みも必要になります。
メルマガ
BtoBのリード獲得として古くから使われている方法としてメルマガがあります。特にBtoBのメルマガの場合は数字を読みやすく、開封率が30%、クリック率が20%(全体の6%)に大体なっていくこともあるため、自社のWEBサイトのCVRが1%だとすると送付数の0.06%となります(メルマガ経由のCVRは高めになる傾向です)。
メルマガの場合、継続的に送付しないとエンゲージメントが高くならず、リード獲得は難しくなります。また、メルマガの文面やコンテンツの質によっても数字にばらつきが出るため、継続的に「顧客が求めるコンテンツ」を配信する必要があります。
また、メルマガの送付頻度が高すぎると、オプトアウト(購読停止)が増えるため、頻度、質、導線を整えながら継続的に配信する必要があります。
アポ代行
リモートワークが増えてアウトバウンドコールの獲得率が下がってきたため、アポイント取得代行のサービスも増えています。「初回商談の意向を得る」までを1件当たりで料金として設定していたり、「初回商談の日程調整まで」や「導入1件あたりのレベニューシェア」など様々なタイプがあります。
また、特定のセグメントに特化して「接点をなかなか作れないエンタープライズ企業」のリード獲得で付加価値を出しているケースもあります。費用感はかなり開きがありますが、BtoBの顧客獲得単価は2万~3万円の企業が多いため、アポイント1件当たりの費用も相場に近い金額が多いです(特定セグメントに特化している場合、費用は高めになります)。
決裁者限定などでリード獲得ができる事もあり、様々な企業が活用しています。
アウトバウンドコールは本当に意味があるのか?
アウトバウンドコールで大事なメンタルケア
アウトバウンドコールにも「ホワイトリスト(コールドコール)」、「リサイクルリード(失注リスト)」、など接点の有無によっていくつか種類がありますが、コールドコールの場合は相場として商談化率(アポ率)が2~3%であることが多いです。
リストさえ入手すれば、リード獲得や商談獲得の方法として確実に数を作ることができます。アウトバウンドコールをする担当者の力量にも依りますが、コールドコールで4%以上のアポイント率を実現できれば、アウトバウンドコールを機能させることができているかと考えられます。
リサイクルリードなど、かつて接点があったリストの場合、商談化率は各段に高くなるため、自社がどういったリードを保有しているか、そのリストが枯渇していないかが重要になります。
数字がある程度見やすく、行動量によってリード獲得ができるため、アウトバウンドコールは強いリード獲得(商談獲得)手法と考えられます。
一方で、アウトバウンドコールを行う担当者のケアが重要となり、アウトバウンドコールのマネージャーによる力量が重要です。セルフコーチングだけでなく組織のビルドアップやメンタルマネジメントなど、アウトバウンドコールのチームを機能させ続けるためにケアが必要です。
というのも、アウトバウンドコールはアポイント率が3%程度となるため、裏を返すと97%断られていることとなります。言い換えると、「100回電話かけて97回断られる仕事」となるため、メンタルケアが大事になります。
アウトバウンドを続けるためには大量のリストが常に必要
また、リストの質と定期的なリストの供給が必要です。リストが枯渇してしまうとアウトバウンドコールする営業先がなくなってしまい、2周目や3周目になります。
同じリードへ電話をかけすぎると、評判にも影響することがあるため、リストをどのように作り続けるかが重要です。さらに、リストも社名などの代表電話だけでなく、ターゲットとなるキーマンのリストであることが重要であり、代表電話番号だけのリストは実質あまり機能しないことがあります(キーマンを知るためのキーマンコールも場合によっては必要になります)。
アウトバウンドコールでチェックしておきたい変化
このように、アウトバウンドコールを継続的に続けるためには「メンタルケア」と「リスト供給」が必要である一方、行動量によって確実に商談を獲得できるため、有効な手法として活用されることが多いです。
このアウトバウンドコールにもいくつかの変化が起きています。1つはリモートワークによる影響です。
従来は電話先であるリード自体が出社していたため、電話も繋ぎやすい状況でしたが、リモートワークによってオフィスにかけても出社していないケースがあり、さらにテレビ会議が増加したことで「ちょっと電話に出る」時間も限られています。
結果的に、「これまでアウトバウンドコールで機能していたけど数字が悪くなった・・」というケースも発生しています。
そんな中、WEBサイトからのリード獲得に注目が集まり、「WEBサイトを閲覧している興味を持ったタイミング」でアプローチする方法として、WEB接客のニーズが高まっています。
WEB接客とは?
WEB接客とは、ウェブサイト上で顧客とのコミュニケーションを行うことです。
具体的には、チャットやメッセージング機能を用いて、顧客からの問い合わせや質問に対応することができます。
自社に興味を持ってWEBサイトへ来訪したお客様に対して、その場でコミュニケーションが可能となるため、「温度感の高い状態」でコミュニケーションが可能です。
結果的に、新規リードを獲得しやすく、同時に”商談化率アップ”も可能な方法です。
また、画面共有やビデオ通話などの機能を備えたシステムを導入することで、よりリアルタイムなコミュニケーションを実現することも可能です。
チャットだけのWEB接客の場合、WEBサイト上でテキストコミュニケーションを行うことでWEB接客を行います。
ほとんどのWEB接客ツールは「専用タグを既存のWEBサイトへ入れるだけ」で導入することが可能であり、導入の手間が少ないこともポイントです。
個人情報がなくても聞きたいことをその場で聞くことができるようになるため、WEBサイトに記載されていない情報を伝えることができるようになります。
WEBサイトの顧客体験を上げる方法としてもWEB接客を活用している企業が多く、企業のブランディングや”おもてなし”としても効果的です。
音声通話も可能なWEB接客ツールの場合、意味合いやニュアンスといった”テキストで伝えにくい情報”もWEBサイト上でコミュニケーションができます。
よりお互いを理解しやすいコミュニケーションを行うことで、WEBサイトからのリード獲得を加速することができます。
「これまで問い合わせをしなかった顧客層」にも自社の魅力を伝える手法であり、WEB接客を通じて新規リード獲得が可能です。
WEBサイトのコンテンツを充実させたり、修正することは時間と手間がかかりますが、WEB接客の場合はPDCAが簡単に回せることも重要です。
さらに、お客様にとっては「その場で知りたい情報をすぐに知れる」という環境になるため、パーソナライズドされたWEB体験が可能となります。
WEB接客はWEBサイト上でお客様とコミュニケーションを取る方法となり、新規顧客獲得やWEBサイト上でのおもてなしができます。チャットタイプや音声タイプなど様々なWEB接客ツールがあります。
WEB接客を通じて、新規商談をインサイドセールスが獲得するだけでなく、インサイドセールス自体がマーケティング志向を持つことができるようになり、顧客体験をアップできるようになりました。
\有人チャットタイプのWEB接客ツールを活用したインサイドセールスの事例/
https://optemo.co.jp/case/sakura-internet/
WEB接客ツールとは
WEB接客ツールとは、文字通りWEB上で顧客とコミュニケーションを取りながら接客するためのツールです。ほとんどの場合WEBサイト上での接客を実現する方法があり、自動的な応対を行うチャットボットがこれまでは主流でしたが、自動化するためのシナリオのPDCAが難しく、有人対応(人がチャットに対応)が多くなりました。
また、テレビ会議ツールが普及し、営業自体がオンライン化した影響で、WEB接客ツール自体もチャットだけでなく、音声で対応できるサービスも増えています。
これまで、有人対応はカスタマーサポートの文脈として主に海外で普及していました。日本でもBtoCなど大規模なサービスではチャットによる有人対応が行われておりました。
最近では、インサイドセールスが組織化された影響によってセールス文脈でも有人でのチャット接客の事例が増えています。
WEB接客はBtoB、BtoC問わず活用されており、PDCAを回していくことによって新規リードを獲得しやすくなります。また、WEB接客で獲得した新規リードは商談化率が高く、その後の受注にも繋がりやすいリード獲得導線となります。
WEB接客ツールのメリット
WEB接客ツールは、新規問い合わせを増やすなどのセールス(営業)用途と、既存顧客からのよくある質問を減らすためのカスタマーサポート用途があります。チャットボットタイプは主にカスタマーサポート用途で活用されることが多いですが、有人タイプのWEB接客ツールはセールス用途で使われることが多いです。
新規リードの獲得
WEB接客ツールを活用すると、セールス用途では新規顧客からの問い合わせを増やすことができます。WEBサイト訪問者の内、問い合わせフォームで個人情報を全て入力するお客様は全体の数%程度となっており、ほとんどのお客様は問い合わせする前にWEBサイトから離脱してしまいます。
WEB接客ツールを活用とすると、「問い合わせは面倒だな・・」と思っているお客様や「問い合わせしようか迷っている」と考えているお客様とその場でコミュニケーションを取り、新規リードを獲得することができます。
有人対応できるWEB接客ツールの場合、WEBサイトに記載されていない情報や魅力をインサイドセールスがその場で補足して伝えることができるため、リード獲得まで誘導することができます。テキストタイプや音声タイプのWEB接客ツールによってコミュニケーションの仕方は異なりますが、自社に合わせた「WEB接客の方法」を確立できると、安定して新規リードを獲得することができます。
商談化率アップ
加えて、WEB接客ツールを通じて獲得した新規リードは「商談化しやすい」という特長があります。WEBサイトへ訪問し、温度感が最も高まったタイミングでそのままコミュニケーションができるため、商談化に持って行きやすくなります。実際、WEB接客ツールの活用企業にヒアリングを行うと、他の導線と比較してWEB接客ツールからの新規リードは商談化率が数倍高くなります。通常の資料ダウンロードでは商談化率が30%だった企業が、WEB接客を通じて商談化率80%を実現している事例もあります。
実際にWEB接客ツールを活用して高い商談化率のリードを獲得している事例も確認してください。
完全にゼロだった可能性を1に広げ、インサイドセールスにとって新たな武器へ
WEBサイトの改善
WEB接客ツールは「WEBサイト訪問者のリアルな期待」が反映されるため、WEBサイトの改善に活用することができます。マーケティングを行っていると、常に仮説に基づいてWEBサイトを改善することになりますが、WEB接客ツールでのお客様のニーズは「WEBサイトを見て感じているお客様の気持ち」となります。したがって、WEB接客ツールを通じて質問されたことやコミュニケーションを取った内容は「WEBサイトを見ていると気になること」になります。
実際に、WEB接客を運用していると「特定の質問を良く受ける」ということが発生します。そこで「WEB接客でよくもらう質問」をWEBページのコンテンツへ反映すると顧客体験が向上したケースもよくあります。
WEB接客をインサイドセールスが行う場合、WEB接客を通じてお客様とコミュニケーションした内容をWEBサイト担当者やマーケティング担当者へフィードバックすることで、会社全体のWEBサイトのパフォーマンスをアップすることができます。
24時間対応が可能
WEB接客は、24時間いつでも顧客からの問い合わせに対応できるため、顧客にとっての利便性が高いと言えます。
チャットボットタイプの場合、営業時間内、時間外に関わらず一定の接客となります。
有人チャットタイプの場合は営業時間内は人が対応して新規リードを獲得し、営業時間外は自動メッセージを活用して接客することができます。
お客様が商品やサービスに関する疑問や不安を持った際に、即座に回答することができるため、購入意欲を高めることができます。
テキストを使ったチャットボットタイプのWEB接客は、工数を全くかけず、お客様にアクションしてもらうことを通じて情報を伝えることが可能です。
人が対応する有人チャットのWEB接客は、営業時間中にリアルタイムで対応することができます。
また、営業時間外であっても自動対応や営業時間外の接客方法に切り替えることができるため、WEB接客ツールの設定を活用しながら24時間対応が可能となります。
通常、WEBサイトは「記載されているコンテンツのみ」で判断されるようになりますが、WEB接客ツールを活用すると、「お客様のニーズに合わせた情報の提供」が可能となります。
チャットボットタイプの場合、お客様が期待している「欲しい情報」に対して、シナリオを適切に組む必要があるため、最初に設定したチャットボットのシナリオで満足せず、最適なWEB接客を実現できているかを確認する必要があります。
有人チャットタイプのWEB接客ツールを活用する場合、チャットや音声通話でお客様の求める情報をヒアリング出来るため、PDCAを回しやすくなります。
営業時間内はインサイドセールスがWEB接客を行い、営業時間外は自動でご案内するようにWEB接客を行っています。今ではWEB接客ツールを通じて、安定して新規商談を獲得できるようになりました。
PDCAを回してWEB接客を活用している事例
https://optemo.co.jp/case/kitera/
リアルタイムでの対応が可能
チャットやビデオ通話を用いたWEB接客は、リアルタイムでのコミュニケーションができるため、顧客との信頼関係をより深めることができます。
従来、WEBサイトは予め用意した文字や画像、動画を見ていただくことで「問い合わせが来ることを待つ」という手段でしたが、WEB接客によって「リアルタイムでコミュニケーションする場」にアップデートすることができます。
お客様が商品やサービスに関する疑問や不安を持った場合に、お客様の立場に立って適切な回答を行うことで、顧客満足度を向上させることができます。
企業自体のブランディングやイメージを向上させることはもちろんですが、WEBサイトを通じた新規顧客が増えるため、「WEBサイト自体のパフォーマンスをアップする」ことに繋がります。
マーケティング部門の主要なKPIとして「新規リード数」を置いている企業も多いですが、WEB接客によって新規リード数自体を増やすことができます。
また、企業によってはマーケティング部門のKPIをリード獲得数ではなく「商談に至ったリード数」もしくは「受注数」に置いている企業もあります。
この場合もWEB接客は効果的で、「温度感の高いお客様をWEB接客でそのまま商談化する」が可能となるため、KPIの改善に寄与することができます。
インサイドセールスの場合、主要なKPIは「商談獲得数」となります。
しかし、その商談の元となるリード数はマーケティング部門が主導しているため、リード数が足りないとKPIの達成は難しくなります。
WEB接客をインサイドセールスが活用すると「新規リードを自分たちで獲得する」が可能となります。
すなわち、これまでコントロール出来なかった「リード数」を自らコントロール出来るようになり、KPI達成を楽にすることができます。
さらに、WEB接客を通じた新規リードは商談化率が高いため、インサイドセールスにとって重要なKPIである商談獲得数を直接アップすることができます。
このように、リアルタイムでお客様とコミュニケーションを行うことで、WEBサイト自体のパフォーマンスをアップするだけでなく、各部門のKPI達成にも貢献します。
インバウンドリードをインサイドセールスが自ら獲得できるようになり、WEB接客を通じてリード数アップはもちろん、商談化数をアップすることができました。
インサイドセールスの新たな武器としてWEB接客を活用している事例
https://optemo.co.jp/case/ub-initial/
複数の顧客と同時にやりとりが可能
電話やメールでの問い合わせに比べ、WEB接客は同時に複数の顧客とやりとりが可能です。
ほとんどのWEB接客ツールは「複数人と同時にチャット」が可能です。
音声通話タイプの場合、1対1でのコミュニケーションとなりますが、チャットの場合は1人で複数人と同時にコミュニケーションができます。
複数人との同時コミュニケーションは一定のトレーニングが必要になるケースもありますが、WEB接客の特長として「あまり工数がかからない」が挙げられます。
顧客1人あたりの対応コストが低減されるため、効率的な顧客対応が可能となります。
例えばインサイドセールス向けWEB接客ツールOPTEMOの場合、「コミュニケーションすべき時に通知でお知らせする」という機能があるため、
インサイドセールスは普段の業務の合間にWEB接客を行うことができます。
導入企業からの声としては「大体1日5~10分程度で新規リードを獲得できる」があり、ほとんど工数をかけずにWEB接客が可能となります。
新規リード獲得導線としてWEB接客を活用している事例
https://optemo.co.jp/case/ub-initial/
顧客の声をリアルタイムに把握できる
WEB接客を利用することで、顧客がどのような疑問や不安を持っているか、どのような商品やサービスに関心を持っているかなどの情報をリアルタイムで把握することができます。
これにより、顧客ニーズに合わせたサービスや商品の提供が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
WEB接客でのお客様からの質問は「WEBサイトを見ているリアルな声」です。
このリアルな声は貴重であり、通常のWEBサイトのPDCAサイクルの中で「お客様のリアルな声」は中々入手することができません。
Google Analytics(GA4)やA/Bテストツール、ヒートマップツールで「アクセスした人のマクロな動き」は確認できても、リアルな声の入手ができません。
結果的にトライアンドエラーが必要になってしまったり、パフォーマンスを上げるために苦労することもあります。
WEB接客ツールを活用すると「生の声」や「リアルな反応」をリアルタイムで把握できるため、WEBサイト自体を改修するためのヒントを得ることができます。
さらに、WEB接客でのコミュニケーションはPDCAを回しやすく、選択肢やコミュニケーションのタイミングを変えることが容易です。
結果的に、従来のマーケティングプロセスよりも早くPDCAを回すことができるようになります。
参考記事:WEB接客とは?使い方から導入まで徹底解説
https://optemo.co.jp/knowhow/livechat-introduction/
顧客情報の蓄積が可能
WEB接客には、チャットログやメッセージ履歴の保存機能があります。
これらの情報を蓄積することで、顧客の問い合わせ履歴や購入履歴を確認することができます。
また、蓄積された情報を分析することで、顧客の傾向やニーズを把握することができ、より的確なマーケティング施策の実施が可能となります。
例えば、「WEB接客で料金に関する質問が多い」という情報を得られると、「WEBサイトは料金に関する情報提供が足りていない」とわかります。
BtoBの場合は意図的に価格を表示していないケースもありますが、この場合も「料金体系の大枠を情報として提供する」は価値となります。
また、このような情報を得られた場合は「ホワイトペーパーとして料金表を作成する」ことも新しい施策として考えられます。
このように、WEB接客で得られた情報を基にニーズを把握し、マーケティング施策へと転換することができます。
インサイドセールスだけでWEB接客を活用したり、逆にマーケティング部門だけでWEB接客を活用するケースもありますが、
理想としては2つの部門が協力しながらWEB接客を活用することが一番望ましい運用のカタチとなります。
WEB接客は新規リードを獲得しながら顧客情報を蓄積し、結果的にWEBサイト全体のパフォーマンスをアップできます。リアルタイムで対応しつつ、営業時間は自動で対応するといった運用が可能となるため、既存のWEBサイトでの顧客対応を強化して新規リードを獲得できます。
WEB接客ツールの種類
WEB接客ツールは主に3種類に分類されます。
ポップアップタイプ
ポップアップタイプは文字通り、特定の条件やセグメントのWEBサイト訪問者に対して、ポップアップを表示してCV(コンバージョン)を促す方法です。
WEBサイトの再訪回数や過去のcookieデータ、購買データ、WEB操作を基にして、クーポンやキャンペーン、資料ダウンロードなどを促す方法です。ポップアップはWEBサイトの全面に出すケースが多いため、ポップアップを出しすぎるとWEB体験自体が損なわれてしまいます。
右下や横の領域にポップアップを出すことも多いですが、気づかれないとクリックされないため、BtoCでは全面に出すケースが多いです(BtoCの場合、スマートフォンからのアクセスも多く、端に表示されるだけではクリック率が低くなりがちです)。また、BtoCではLINEの友達登録やInstagramへの誘導など、SNSへの誘導として利用されることもあります。
BtoBの場合、全面だけでなくサイドバーや右下などに表示することも多いですが、魅力的な情報を提供しないとクリック率がアップしません。また、クリエイティブによってクリック率も変わるため、ポップアップのデザインを定期的に見直す方が効果を安定化させることができます。
また、「当たるクリエイティブ」を見つけるまでにPDCAを回すことによって、一定の成果を上げることができます。
企業側が誘導したいページへポップアップによってアクセスさせることができるため、WEBサイトでのカスタマージャーニーとして設計することができます。
しかし、「お客様の期待」に合わないポップアップやデザイン(画像のクリエイティブ)の場合はクリック率が低くなり、WEB接客としてのパフォーマンスが出にくくなります。
自社にデザインができる体制がある方がPDCAを回しやすくなります。
ポップアップタイムのWEB接客ツールはマーケティング部門が主導して行われますが、WEB接客での結果をWEBサイト自体に反映することも重要です。WEB接客での反応は「リアルなお客様のニーズ」となるため、そのニーズに合わせたWEBページを新たに作成することで、WEBサイト全体のパフォーマンスアップすることができます。
チャットタイプ
チャットを通じてWEBサイト上で接客する方法です。LINEやSlack、chatworkなど日常生活でチャットを使う機会が増えているため、チャットを使って欲しい情報をダイレクトに入手させることができます。
チャットボットを使った無人での対応と、有人でのチャットサポートを行うケースがあります。
チャットボットの場合、事前に設定したシナリオを基に、WEBサイト訪問者とインタラクティブなコミュニケーションが可能です。しかし、シナリオを最適化しないとWEB体験が落ちてしまい、WEBサイト訪問者は使わなくなってしまいます。
例えば、「資料請求をしたい」、「見積をしたい」、「機能を知りたい」などいくつかのボタンを設置して、さらにいくつか質問をした上で「このページへアクセスしてください」といった結果になると、チャットボットとしては有効ではありません。
WEBサイト訪問者へアクションを取ってもらうことは負荷がかかるため、それだけ”質のいい情報”を提供する必要があります。自社のWEBサイトへ訪問した方がどんな情報を期待しているのかを知る必要があるため、シナリオはPDCAを回すことが必要です。
しかし、定期的にPDCAを回すことができないケースもあり、活用する場合はPDCAを回すことを前提としたうえで進める必要があります。
有人対応の場合、きめ細かい接客ができるため、WEBサイト訪問者が求める情報をタイムリーに提供することができます。
結果的に「後日連絡を取る」や「別途資料を送る」などリード情報を獲得してCVが可能です。一方、有人対応の場合は「どのページに表示するか」が大事になります。
WEBサイト訪問者が好きなタイミングでチャットを始めることができるため、トップページに表示すると様々な問い合わせ、要望が届きます。カスタマーサポートとセールスが近い会社であれば問題ないですが、部署として分かれていると「WEBサイトには様々な方がくる」可能性があるため、セールスとカスタマーサポートで切り分けることができなくなります。
どのページに表示するかを最適化する必要がありますが、多くの企業で「トップページのPVが圧倒的に多い」ケースが多いため、ボリューム調整が難しいです。
以前はチャットボットを使ったシナリオ型のWEB接客が主流でしたが、PDCAを回すことが難しいため、有人対応に切り替えている企業も増えています。
有人チャットでWEB接客を行う場合、WEB接客に合わせたコミュニケーションを行うことが重要です。WEB接客では「端的に、素早く」が重要となります。5行以上の文章で伝えようと思うと、WEB接客では上手くコミュニケーションができなくなります。端的で的確な情報提供をWEB接客では行うことが成果を上げるポイントになります。
音声タイプ
Zoomやteams、Google Meetなどテレビ会議ツールを使った営業が増えた影響により、WEBサイト上での接客も音声を使った方法が増えています。
WEBサイト上でそのまま音声によるコミュニケーションを行い、”プレ商談”を行うことでお互いを理解してその先へ進めることができます。音声会話ができるWEB接客ツールは、「コンバージョンしたお客様が商談に繋がりやすい」という特長があります。
WEBサイト上で音声会話を一度行うと、お互いに信頼関係が生まれ、次にもう一度コミュニケーションを取る際にお互いの抵抗感が低くなります。WEB接客を行った後のコネクト率も高くなるため、WEBサイト上で音声会話を行うことは効果的となります。
フォーム入力してから音声で商談するツールもあれば、個人情報は不要で音声コミュニケーションを始めるツールもあります。個人情報は不要で音声会話ができるWEB接客ツールの場合、「まだ温度感が高くない」お客様に対して音声で魅力を伝えることができるため、インサイドセールスにとっては使いやすくなります。
平行してチャットも使えるWEB接客ツールもあるため、「意味合いやニュアンス」は音声でコミュニケーションし、「文字で伝えたほうが良いこと」はチャットを使ってコミュニケーションが可能です。
これまでのWEBサイトは「まずは全て個人情報を入れてください」から始まる商習慣でしたが、音声でのコミュニケーションを個人情報なしで行うことができるため、「詳細な商談に進むべきか」を手軽に確認することができます。
体感としても、「5分くらい話せば可能性があるかわかる」ケースも多いため、WEBサイト上で気軽に行うことが可能です。
近年ではオンライン会議も社内外含めて普及し、リモートワークなどによって「会議自体が増えた」ケースもあり、「とりあえず時間をとって話をする」が負荷になっています。
音声を使ったWEB接客では”プレ商談”としてサッと話を出来るため、お互いに効率的に時間活用が可能です。
WEB接客ツールを比較する時のポイントはこちらの記事もご確認下さい。
必要な機能や選ぶポイントを解説しています。
WEB接客に必要な機能とは?WEB接客ツールを比較する時のポイントを事例で紹介
ビジネスに与える効果
WEB接客は、上記のメリットから、ビジネスに多くの効果をもたらします。具体的には、以下のような効果があります。
販売促進効果(新規リード獲得、新規商談獲得)
WEB接客を利用することで、顧客の購入意欲を高めることができます。
現在のWEBサイトに記載されている情報だけでは温度感を高めることができないお客様であっても、WEB接客を通じてコミュニケーションを行うことによって、
自社の魅力やサービスの魅力、「お客様の課題を解決するソリューション」を伝えることができるようになります。
結果的に新規リード獲得や新規商談獲得が可能となるため、WEBサイト全体のパフォーマンスをアップすることができます。
特に、新規リード獲得と新規商談獲得はマーケティング部門とインサイドセールス部門にとって重要なKPIであり、その重要なKPIをWEB接客で改善することができます。
リアルタイムでのコミュニケーションや、24時間対応が可能な点が、購入に至るまでの時間を短縮し、スムーズな購入体験を提供することができるためです。
さらに、WEB接客ツールではパーソナライズドされた情報提供が可能となるため、
例えば「WEB広告から流入したお客様にはこのタイミングでこういったコミュニケーションをしよう」や
「機能ページを見た後に質問ページを見たお客様には運用に関するコミュニケーションをしよう」といった「お客様の期待値に合わせたコミュニケーション」を簡単に設定することができます。
WEB接客なしではできなかった「パーソナライズド」を簡単に行えるだけでなく、そのPDCA自体もドンドン回すことができます。
WEB接客を活用して新規リードを獲得している事例
https://optemo.co.jp/case/i-station/
顧客満足度の向上
WEB接客は、顧客とのコミュニケーションを円滑にし、顧客満足度の向上につながります。
予め用意したコンテンツをお客様に探してもらうというWEBサイトではなく、「気になることに対してその場で情報提供する」というWEBサイトにすることができるため、お客様にとってのWEB体験を向上することができます。
WEB接客ツールを活用している企業でのログデータでよくある情報ですが、コミュニケーションの中でお互いに「ありがとうございます」と連絡することが多くなり、
従来のWEBサイトでは見られなかったコミュニケーションが発生します。
顧客の疑問や不安を適切に解消し、ニーズに合わせた商品やサービスを提供することができるため、顧客が満足する買い物体験を提供することができます。
注意しなくてはいけないことは、「WEB接客を画一的なコミュニケーションにしてしまう」ことです。
当然ですがWEB接客で相手にしている方は「ヒト」であり、「お客様」です。
向こう側に人がいるということを意識してコミュニケーションすることが大事です。
WEB接客でよくある失敗としては「オペレーションをガチガチに決めてしまい、定型文だけ送り続ける」です。
このように「先にオペレーションを決めてしまい、あとは回すだけ」という思考でWEB接客を行うと、確実に失敗してしまいます。
なぜならお客様にとっても良くないWEB体験となってしまい、顧客満足度が上がりません。
WEB接客で大事なことは「画面の向こう側にいるお客様と向き合うこと」です。
当たり前のように感じるこの考えを大事にすることで、顧客満足度をアップすることができます。
参考記事:BtoBインサイドセールスのためのWEB接客入門
https://optemo.co.jp/knowhow/btob-livechat/
コスト削減効果
WEB接客を利用することで、顧客1人あたりの対応コストが低減されるため、コスト削減につながります。
通常、BDRの場合はターゲティングしたお客様に対してアポイント率数%でアポイントや商談を獲得します。
SDRの場合はインバウンド経由だと30~50%程度になりますが、リード数が十分にないと「失注リードばかりにアプローチする」となります。
アポイントは取れても実は効率的でないこともあり、合わせてインサイドセールスの担当にとって「辛い架電」となってしまいます。
WEB接客は複数人と同時にコミュニケーションを行ったり、通常業務の合間に新規リード獲得が可能です。
工数をほとんどかける必要がないため、効率的なリード獲得、新規商談獲得が可能です。
さらに、WEB接客では「自社のサービスに興味を持ったお客様」とコミュニケーションが可能となります。
だからこそ、インサイドセールスの担当にとって「コミュニケーションしやすい業務」にすることができます。
インサイドセールスのモチベーションが下がるとパフォーマンス自体が下がってしまいますが、WEB接客を通じた「自社を求めているお客様」とのコミュニケーションを業務に入れることで、
モチベーションをアップさせて通常業務のパフォーマンス自体も向上することができます。
WEB接客を活用してインサイドセールスのスキルアップも実現している事例
https://optemo.co.jp/case/kitera/
顧客情報の蓄積と分析によるマーケティング施策の向上
WEB接客で蓄積された顧客情報を分析することで、顧客のニーズや傾向を把握し、それに基づいたマーケティング施策を打つことができます。
WEB接客を活用しているある企業では「これまでWEBサイトに来るお客様は課題の解決策を探しに来ている」と思っていましたが、
WEB接客で実際のデータを見ると「料金が気になっている企業がほとんど」であったこともあります。
結果的に、WEBサイト自体の料金に関する情報提供を強化することで、WEBサイト自体のパフォーマンスがアップし、新規リード数が向上しました。
このようなケースはよくあり、WEB接客を初めて活用した企業は何かしらの新たな「気づき」を得ることがほとんどです。
このように、WEB接客には「WEBサイトを見ているお客様のリアルな情報」が蓄積するため、分析を通じてマーケティング施策自体を向上することができます。
具体的には、特定の顧客層に向けたキャンペーンや、新商品の開発、既存商品の改善などが考えられます。
WEB接客で新たなマーケティング施策も可能です。
例えば、WEBサイトへ来訪することが初めての方に対するコミュニケーションと、5回目に来訪するお客様とのコミュニケーションに変化をつけ、
5回目の方だけの限定のキャンペーンを実施することで、「気になっているけど問い合わせしようか迷っている」というお客様の背中を押すことができます。
WEB接客はパーソナライズドした体験の提供が可能となるため、WEB接客で入手した顧客情報を基に新たなマーケティング施策が可能です。
インサイドセールス向けWEB接客ツールOPTEMOでは、下記のような情報に応じた設定が可能です。
・時間、曜日
・WEBアクセス(URL)
・滞在時間
・WEBサイト来訪回数
・PC、スマートフォン、タブレットなどのデバイス
・MAに登録されているかどうか他にも様々な情報でWEB接客をパーソナライズドすることができます。
OPTEMOの資料はこちらから
https://optemo.co.jp/#request
競合優位の確保
WEB接客は、従来の電話対応やメール対応に比べ、迅速でスムーズな対応が可能であるため、競合他社との差別化ができるというメリットがあります。
例えば、競合企業では「WEBサイトを見てもらい、気になったら問い合わせして数日後に回答」となっている場合はチャンスです。
このようなケースでは「気になるけど情報を得られるまで時間かかるし、色々電話来て面倒だ」と考えて問い合わせしなくなるケースもあります。
自社でWEB接客を活用すると「ちょっと気になったので聞きたいです」というコミュニケーションの入り口を用意することができるため、こういった「競合と比較しているお客様」に対して先行してコミュニケーションができます。
お客様は最初に問い合わせをした企業で決める可能性が高いため、どれだけ早期にコミュニケーションを取れるかは非常に重要な要素となります。
加えて、「WEB接客でいつでも聞ける会社」と「問い合わせして連絡を待たないとコミュニケーションできない会社」だと全社の方が顧客体験として優れています。
WEBサイト自体の体験をアップデートさせながら、新規リード獲得ができる方法として、WEB接客の活用がポイントになります。
さらに、顧客情報を蓄積して分析することで、より効果的なマーケティング施策を行うことができ、競合他社よりも先進的なサービス提供を行うことができます。
WEB接客ツールをBtoBで使う時の悩み
WEB接客ツールをBtoBで使う際、よく聞かれる声として下記があります。
・経験のあるメンバーが対応しないと質問に答えられないのではないか?
・工数対比でどのくらいリードや商談を獲得できるかわからない
・マーケ部門とインサイドセールス部門の連携が取れない
・ターゲット以外の対応が増えてしまい、効率が下がることが怖い
BtoBの場合、WEBサイト訪問者から様々な問い合わせ、質問が来るケースがあります。その質問へ適切に対応するためにはジュニア層のメンバーではなく経験者が対応しないと対応しきれないことがあるという悩みがあります。しかし、実際の利用者の声を聞くと「詳しい情報をお調べしてご連絡させていただきますのでメールアドレスを教えていただけますか?」と一次対応をして(BtoBだからこそ)問題ないケースが多いです。結果的に、詳しい情報を回答することを通じてコンバージョンし、そこからコミュニケーションを行っているケースが多いです。一方、ベテランの担当が対応することに越したことはないですが、ベテランになればなるほど忙しいことが多いです。
自社でWEB接客ツールを使えるのか?
BtoBでリード不足の時、WEB接客ツールは使えます。但し、自社のWEBサイトの特性や、WEBサイト訪問者がどういったニーズで自社のWEBサイトへ来ているかなど「自社WEBサイトへの理解」が必要になります。しかし、多くの場合で「想定していた仮説と違った」というケースも多いため、検証しながら理解するという進め方が重要になります。
【1枚モノのLPの場合】
例えばWEBサイトがLPの場合、SEOからの流入が少なく、広告をメインとした導線になります。この場合、WEBページの滞在時間は5~10秒であるケースが多く、広告経由の流入の場合は滞在時間が短くなる傾向があります。また、LP自体のコンテンツ量によっても滞在時間が変わってきますが、長いLPであっても30秒以内の滞在時間がほとんどのケースかと思われます。Google Analyticsなどの数字を見るともっと滞在時間が長めになりますが、社内からのアクセスや一部の方が長く滞在する影響で「滞在時間」自体は長くなる傾向があります。ほとんどのケースはGoogle Analyticsよりも短めになっているという想定が必要です。
この時、WEB接客ツールとしてアプローチする方法は「いかに最短でメリットを伝えるか」が大事になります。じっくり話をするという切り口でWEB接客を行っても訪問者は離脱してしまうため、端的に「○○をプレゼントしています。ご希望されますか?」のようにメリットを端的に表現する必要があります。リードとしてCVするためには「5秒の中でどうコミュニケーションをとるか」を主眼に置き、「5秒で何を求めているのか?」を当てる必要があります。
例えば、「料金が知りたい」と思っているWEB訪問者に対して、「機能をご紹介します」とお声がけをしても、WEB接客としてはコミュニケーションが取れず、リード獲得ができません。
いくつかの切り口でPDCAを回すことによって「自社のLPに訪問した方の求めるニーズ」を明らかにする必要があります。
【サービスサイトの場合】
WEBサイトがサービスサイトの場合、複数のページでWEB接客する切り口があります。サービスサイトの場合、機能や価格、事例、イベント情報、よくある質問などWEBサイトを回遊することが多いため、TOPページでいきなりWEB接客をしてもコンバージョンには至らず、リード獲得できないこともあります。TOPページでWEB接客する場合は、滞在時間がある程度長めの方や、ある程度スクロールしている方などを狙い撃ちにしてアプローチすることでリード獲得しやすくなります。
また、機能ページや価格ページなど、個別のページでは、そのページの特性に合わせてWEB接客を行うことで、リード獲得することが可能になります。例えば、価格のページでは「あなたに合わせた価格を今すぐお見積りします」といった切り口でコミュニケーションを取ることによってWEB接客を最適化することができます。
このように、自社のWEBサイトの特性に合わせてWEB接客を構築することで、BtoBであってもWEB接客でリード不足を解消することができます。
SaaS企業がWEB接客ツールをBtoBで使う方法
WEB接客ツールを使う上で考えておきたいこと
WEB接客ツールを使う上で考えておきたいことは下記となります。特に、BtoBのSaaSの場合は下記が重要となります。
1.自社のWEBサイトはどのくらい「アツい顧客」を流入させているか
Google Analyticsなどでの数字としてのセッション数だけでなく、自社のターゲットとなる顧客がどの程度流入しているかが大事になります。例えば広告の場合、ある程度セグメントされたリード候補が流入していますが、ほとんど温度感がない状態からのスタートになります。そこでWEBサイトのコンテンツが十分にある場合、WEBサイトを顧客が回遊することで温度感が上がることがあります。一方、LPでかつコンテンツが少ない場合、広告での流入は多いものの、アツい顧客は実質少ないケースもあります。SEOでの流入の場合、回遊することで滞在時間が長くなりますが、ターゲット顧客以外の流入や、まだニーズが顕在化していないケースもあります。情報収集段階でWEB接客を行ってもコンバージョンまで至らず、リード獲得できないこともあります。自社のWEBサイトにどういった顧客が流入しているかによって、接客の仕方も異なります。
2.自社のWEBサイトへの訪問者はどんな情報を入手したいと思っているのか
自社のWEBサイトに訪問している方がどういった情報を入手したいと思っているかによって、接客の仕方が変わります。BtoBの場合、「感情的な衝動買い」は少なく、合理的な判断によって購買行動が行われます。だからこそ、料金を知りたいと思っているのか、機能を知りたいと思っているのか、課題を解決する方法を知りたいと思っているかによって接客の仕方が異なります。また、ニーズの中でもどういった声のかけ方をするかによっても成果が大きく変わります。例えば、「何かご不明点がありましたらお気軽にチャットでご連絡下さい。」という切り口でWEB接客をする場合がよくありますが、このようなオープンクエスチョンだとコミュニケーションを取れずにリード獲得できないことが多いです。一方で、「今すぐあなたに合わせた費用をお見積りします」といったメッセージによってリードを獲得することもできます。ただし、費用を知りたいと思っているWEB訪問者に最適なケースとなり、別のニーズの方には刺さらないWEB接客になります。
3.PDCAを回して最適化していくこと
WEB接客は最初の仮説で全て当たるケースはほとんどありません。また、時流やマーケ施策によってWEB訪問者が求めるニーズは変化していきます。だからこそ、BtoBでWEB接客を行う場合はPDCAを回して改善活動を続けることが重要となります。どんなニーズが一番訪問者の求めている情報であるか、いくつかのケースでPDCAを回し、リード獲得を最適化していくことが重要です。最初に設計したが、そこからPDCAが回らないというケースも多く、「最初の設計は外れるもの」と考えた上でPDCAを回していくことがBtoBで一番リード獲得を出来る方法となります。特にSaaSの場合、The Model型の営業体制を取っていることも多く、インサイドセールスとマーケティング部門が連携することでリード不足を解消することができます。PDCAを回しながら改善活動を一緒に行っていくことが全体最適となっていきます。
WEB接客ツールの種類を選ぶ
WEB接客ツールの種類を選ぶポイントは下記になります。
【チャットボット型】
出来るだけ放置してリード獲得を行う場合、チャットボット型のWEB接客ツールが最適となります。この時、WEBサイトに一番詳しいマーケティング部門が担当するケースが多くなります。チャットボット型の場合、特にPDCAが大事になります。そして、チャットボットを使ってWEB訪問者のどういったニーズにこたえていくか、WEB体験を設計することが重要です。色々回答してもらった結果、特定のページを案内するだけのシナリオとなる場合、WEB訪問者は「期待値」がなくなるため、反応しなくなっていってしまいます。
【有人チャット型】
有人チャットで対応する場合、どこのページで対応をするかが重要になります。TOPページでは色々な訪問者がいるため、既存顧客やターゲットではない訪問者にも対応することを想定する必要があります。一方、特定のページだけで接客を行う場合、母数が少なくなる可能性もあるため、WEBページのどこで接客を行うかがリード不足解消のカギになります。また、チャットだけでコミュニケーションを取っていくため、どこまでWEB接客を行い、どこでトスアップをするかも大事になります。チャットのみではWEBサイト訪問者の背景や意図を完全に理解することが難しくなるため、どういった切り口でコミュニケーションを取っていくかが重要になります。
【音声通話付きWEB接客ツール】
音声通話付きWEB接客ツールを使用する場合、どのタイミングでコミュニケーションを取るかが重要になります。WEBサイトへ訪問した直後にコミュニケーションを始めようとしても、訪問者からすると「いやいやまだWEBサイトみたいんだ」となりコンバージョンまで至りません。しかし、遅すぎるとWEBサイトから離脱してしまいます。どのタイミングでのコミュニケーションが最適であるかを設計する必要があります。多くの企業に共通していることは、「問い合わせページ」です。問い合わせページのセッション数に対して実際のCV数が少ないケースもあり、問い合わせページでの離脱が多いです。ここでコミュニケーションを取ることにより、知らず知らずに逃していたサイレントカスタマーを獲得することができます。
【音声タイプのWEB接客ツールを活用した事例はこちら】
完全にゼロだった可能性を1に広げ、インサイドセールスにとって新たな武器へ
BtoBだからこそWEB接客ツールで心得たい事
BtoBだからこそWEB接客ツールで心得たい事は、PDCAを回すことです。一番シンプルで一番難しいことがPDCAを回すことであり、リード不足を解消するために必要なことがPDCAを回すことです。どうしても改善活動を止めてしまうことが多いですが、リード獲得するためにはPDCAを回すことが一番重要です。どのWEB接客ツールを使う場合においても、PDCAを回すことができないと十分な効果を発揮することができなくなります。
特にBtoBの場合は自社のサービスの位置づけ、WEBサイトのコンテンツ力、流入導線によって最適な接客の仕方が変わるため、WEBサイトの訪問者の求める情報でなければリードを獲得することができなくなります。
特に、インサイドセールスは日々の業務で忙しく、改善に時間を割くことが難しくなってしまいます。PDCAを回せず日々の業務に忙殺されると、結果的にリード不足のための施策を打てなくなり、アウトバウンドコールに依存していくという流れになります。アウトバウンドコール自体は悪くないですが、PDCAを回すことができないとアウトバウンドコールもドンドン機械的になってしまいます。
そうなるとリード獲得のために疲弊していってしまうため、PDCAは非常に重要な要素となります。
逆にWEB接客ツールのPDCAが回っていくと、「自社に興味のある顧客とコミュニケーションを取っていく」というインサイドセールスの業務になっていくため、インサイドセールスとしてのやりがいがよりアップしていきます。
WEB接客ツールを使う手順
WEB接客ツールを使う手順は下記になります。
1.使うツールを選定する
チャットボット型、有人チャット型、音声通話付きなど使うツールを選定します。インサイドセールスが利用するケースなど、セールス用途でWEB接客ツールを活用する場合、音声通話付きのツールが有効です。インサイドセールスは音声での会話を通じて営業することが得意であり、WEB接客ツールでも強みである音声を活かせるタイプがおススメです。
2.目標を設定する
WEB接客ツールを使ってどのくらいのリードを獲得したいか、アポイントを獲得したいかの目標を立てます。WEB接客ツール自体の費用、WEB接客ツールの工数を鑑みて、ROI(費用対効果)が合うように目標設定を行うことがポイントです。自社が現在「1件のリードを獲得するためにいくらかかっているか」というCV単価や、「1件の商談を獲得するためにいくらかかっているか」という商談単価を確認すると、目標を明確に決めることが可能です。
3.最初の仮説を立てる
既存のWEBサイトでの訪問者のニーズと接点について仮説を立てます。仮説を立てたらWEB接客ツールを使って検証を開始します。ここで気をつけたいポイントは、「最初の仮説は外れやすい」です。最初に仮説をガチガチに決め、オペレーションまでガチガチにしてしまうと、かえってWEB接客ツールを上手く活用できないこともあります。最初の仮説は重要となりますが、WEBサイトの実態に応じて検証していく気持ちが重要です。
特に、「WEBサイトへ訪問している方のリアルな気持ち」を知る機会はあまりないため、WEB接客ツールを通じて得られた情報を基に、仮説を検証して改善することが大事です。
4.改善を始める
改善を定期的に行います。WEBサイトの様々な切り口でWEB接客を行い、どんな訪問者がどんなニーズを持ってWEBサイトを訪問しているかを確認します。
そのニーズに応じてWEB接客を行い、リードを獲得しながらPDCAを回していきます。
PDCAを回さないとWEB接客は上手くパフォーマンスを発揮できなくなります。だからこそ、PDCAを回すことを念頭にして始めることが大事です。
WEB接客ツールの弱点!?
WEB接客ツールの課題は3つ
WEB接客ツールはリード不足解消のための万能なツールではないため、弱点があります。
1.受動的なツールの場合、アプローチができない
WEB接客ツールのチャットボット型の場合、アイコンをクリックされないと始めることができないツールもあります。この場合、WEBサイト訪問者が自発的にクリックをしないとコミュニケーションを開始することができません。企業側からアプローチができないため、受動的なコミュニケーションとなってしまいます。企業がアプローチしたいタイミングでコミュニケーションを始めるためには、能動的なアプローチができるツールを選定する必要があります。一方、能動的なアプローチができるWEB接客ツールであっても、いきなりガンガンコミュニケーションを取るとWEB体験自体が落ちてしまい、結果的にリード獲得できなくなりますので注意が必要です。
2.WEBサイトのコンテンツ力に依存する
WEB接客ツールは「WEBサイトに訪問している間」に使うツールとなるため、WEBサイト自体にコンテンツ力がないとコミュニケーションが取りづらく、リード獲得が難しくなることがあります。内容が薄いLPや簡単なコーポレートサイトの場合、WEBサイトの滞在時間が短く、WEB訪問者の温度感が上がりにくいためWEB接客ツールが機能しにくくになります。
3.チャットだけの場合、最適な情報提供をしきれない
チャットを通じたWEB接客でリードを獲得する場合、チャットだけでは「背景やニュアンス、意図」を完全に把握することが難しいです。端的なコミュニケーションでニーズをつかむことが重要となります。また、音声通話付きWEB接客ツールを活用すると、WEBサイト上でそのまま音声通話が可能となるため、ニュアンスや意味合いをつかみやすくなります。近年、テレビ会議ツールを活用した営業が一般的となっているため、初めてのコミュニケーションをWEB上で行う抵抗感が少なくなっており、音声通話付きWEB接客も抵抗がなくなってきています。
BtoBで始まっている新たなWEB接客ツール
BtoBでのWEB接客ツールは近年注目を集めて様々な企業が導入をしています。特にBtoB向けSaaS企業の場合はThe Model型の営業組織となっており、インサイドセールスの組織化が進んでいます。一方で、インサイドセールスが十分にワークするためにはリードが必要不可欠となりますが、様々な施策を打ってもリード不足が慢性化している企業も多くなっています。そこで、WEBサイトからインサイドセールスがリードを獲得し、そのまま商談アポイントまで持って行くことができるWEB接客ツールに注目が集まっています。
WEB上で音声コミュニケーションを行う
WEB接客ツールの中での新たな流れが音声コミュニケーションです。従来のWEB接客ツールはチャットのみの対応でしたが、Zoomやteams、Google Meetなどテレビ会議ツールが一般化したことにより、オンラインでのコミュニケーションが当たり前になりました。結果的にWEB接客ツールもチャットのようなテキストコミュニケーションだけでなく、音声通話が可能なWEB接客ツールが増えています。音声を使ってコミュニケーションを行うことでリード顧客の背景や意図、ニュアンスを知ることができるため、お互いが求める情報を提供することが可能となり、結果的にリード獲得することができます。また、音声の場合その場での日程調整などもしやすくなるため、リードを獲得してそのまま商談アポイントまで持って行くことも可能です。
コミュニケーションのタイミングを最適化する
従来のWEB接客ツールは「どこのページに入れるか」のみの設定でした。しかし、そのページを見ていても「見たばかりのタイミングでコミュニケーションと言われても・・」となってしまいます。そこで今は「どのページにどのくらい滞在したタイミングでコミュニケーションを取るか」を設定できるようになってきています。例えば、「価格ページを30秒見たタイミング」など「ちょうど今話を聞きたい」タイミングでコミュニケーションを取れるようになっています。
WEB訪問者がどこを見ているかがわかる
WEBサイトでのコミュニケーションの場合、「ここに書いてあることを聞きたいんだけど・・」となってもどこを見ているかわからないことがあります。電話でコミュニケーションを取っていても同様のことが起こり、「ここって言われてもどこをみているんだろう?」となります。現在のWEB接客ツールは「WEB訪問者が見ている画面」を見ることができるようになっているため、企業と顧客が一緒にWEBサイトを見ながらコミュニケーションを取っていくことが可能です。より自然なコミュニケーションとなるため、リード獲得もしやすくなります。特にBtoBの場合、業務時間内は時間が限られるため、お互いに効率的で自然なコミュニケーションのためにも「どこを見ているか可視化されている」ツールを選ぶことが重要です。
OPTEMOについて
株式会社OPTEMOが運営するOPTEMOは3つの機能があります。
1.WEBサイト訪問者が見ている画面をリアルタイムで可視化
WEBサイト訪問者が見ている画面をリアルタイムで可視化することができます。従来ツールのような「URL」だけでなく、そのページのどこの部分を今見て気になっているのかをリアルタイムで把握することができます。今見ている画面がわかるからこそ、より自然なコミュニケーションとなり、リードを獲得しやすくなります。
2.今見ているWEBサイト上でワンクリックすると音声通話が可能
個人情報やツールのインストールは不要であり、クリックするだけで音声通話が可能です。電話番号なども使っていないため、「ちょっと話す」という体験を既存のWEBサイトですぐに実現することができます。また、会話中に手元の資料を共有するなど画面共有の機能もあるため、WEBに載っていない手元資料を見せながらコミュニケーションを取ることも可能であり、お互いが納得しながら商談へ進むことができます。
3.特定のWEBアクセスをした顧客とコミュニケーションが可能
WEBサイトには色々な訪問者がいるため、その中でも特定のWEBアクセスをした訪問者とコミュニケーションが可能です。「このページに20秒滞在したタイミング」などを何個でも自由に設定できるため、自社のWEBサイトに合わせた「温度感が高い最適なタイミング」でコミュニケーションが可能です。
Slackやteams、Chatwork、Google Chatに通知が届くため、普段は別業務を行いながら、通知が来たらWEB接客を行うという運用の仕方でお使いいただくことが可能です。
OPTEMOについての詳細はお気軽にお問い合わせください。
また、本ページにある電話アイコンを押すと、担当者とそのままコミュニケーションが可能です(営業時間内のみ表示されます。)
BtoBのリード不足を解消するWEB接客ツールOPTEMOの資料を是非ご覧ください。